冬季の里山探索は「飯盛山」から「高安山」へ

2016年前半のハイライトは「飯盛山の全ルートを歩く計画」でした。夏の暑い時期は歩ける距離がどうしても短くなります。駅前から手軽にアプローチできる「飯盛山」は、とても好都合な探索エリアだと言えるでしょう。
link1
様々な出会いと発見があった「飯盛山」。とりわけ、妙見谷堰堤の下に広がる「観察の森/里山ガーデン」の大銀杏に感激しました。
スポンサーリンク
「教照寺ルート」で締めくくる
mymap
締めくくると言っても、しばらくは重点エリアを高安山へ移すだけ。桜の咲く頃に再訪を予定しています。四條畷神社から新道付近に、面白い分岐道がまだまだありそうです。地図には全く記載されていないので、マイマップに情報を追記しておきました。
いよいよ舞台は「高安山」へ
全天球カメラTheta SCフィールド・テストin高安山 – 2016年12月10日 – ヤマレコ
link2
今季の「高安山越十二道」歩きに相応しいルートをチョイスして歩いてきました。神光寺道は地理院地図に破線で表記されていますが、標高250m付近までは勾配のキツイ登りで、頭まですっぽり覆いかぶさる笹のヤブ漕ぎを強いられます。
ヤブ漕ぎ地帯を抜けると、奇岩と巨岩の織り成す興味深い尾根道となり、古代高安城との関連を妄想しながら歩くのがとても楽しいのです。今季の目標は楽音寺道の解明と立石越本道ルートの整備です。
ストリートビューで古墳を探検しよう!
「高安山越十二道」探索の中間まとめをGoogleマイマップでご報告
link3
「高安山越十二道」探索の中間まとめをGoogleマイマップで報告した際に、文献資料で知識を補充することを決意していました。しかし、時が経つのは速いもので、あっという間に冬になってしまい、充電期間どころの騒ぎではありません。(言い訳やろ)
売り上げランキング: 118,365
amazon
代わりに高安古墳群のいくつかを360°パノラマ写真で撮影し、ストリートビュー(インドアビュー)として公開しました。(今後も撮影を計画しています)
服部川43号墳
神光寺墓地内にある二基の古墳の内、道路に面した場所にある古墳です。最奥まで入って天井の様子もご覧いただけます。
大窪・山畑7号墳
ここは通称「抜塚」として知られています。なんと、その名の通り古墳の内部を「通り抜け」できますよ。通行の際には頭を低くして歩いてくださいね。
売り上げランキング: 845
amazon
いずれも一定間隔で撮影した複数の360°パノラマ画像を、画像下の矢印で繋いでいます。いずれかの矢印をクリック(タップ)するとこで、その方向に移動できます。今年の10月に発売された廉価版のTheta SCで撮影しました。Google CardboardなどのVRゴーグルを使用すると、その場に居るかのようなバーチャル体験が可能です。上掲のゴーグルは段ボール製ですが、安価に楽しめるもので、騙されたと思って一度お試しになってくださいね。
自分で撮影した全天球パノラマ写真をGoogle Cardboardで見せたらバカ受けした件
link4
今後も生駒山系を舞台に、バーチャル体験ができる面白いコンテンツを提供していこうと思っています。静止画だけでなく動画作成にも挑戦中。もちろん、動画だって360°思いのままにグリグリできますよ。
youtube
では、また。
ad
ad
関連記事
-

-
大阪府民の森・あじさい園(ぬかた園地)を100パー楽しむためのガイド
あじさいまつり2016年バージョンはコチラ 大阪府民の森・ぬかた園地では、毎年6 …
-

-
王龍禅寺の磨崖仏・十一面観音菩薩像にご対面して来ました。
海瀧山王龍寺(王龍禅寺とも言う)は、奈良市の西部にあって北に「あすかの台」の新興 …
-

-
生駒山の自然を歩く会・第3幕
矢田峠 第3幕開演です。 写真は五丁石から北へ進んだところにある矢田峠です。 オ …
-

-
予定は未定の一年を振り返る。
今年は計画的に山歩きしようと決めました。暑くて歩けない8月以外は、順調だったと思 …
-

-
アウトドアの新定番YAMAP(ヤマップ)のモニターキャンペーン「お味噌汁の巻」に応募した
『ただいまYAMAPでは、登山食で定番の「お味噌汁」に関して、モニターキャンペー …
-

-
「生駒山系まるごとハイキングマップ」リニューアルのお知らせ
大阪府民の森を管理する「大阪府みどり公社」は、「生駒山系まるごとハイキングマップ …
-
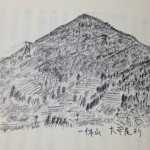
-
山の良書Ⅰ – 「大和まほろばの山旅―奈良県北・中部の山」
「良い山歩きに良書あり」- インターネットが今ほど普及していなかった前世紀のお話 …
-

-
自分で撮影した全天球パノラマ写真をGoogle Cardboardで見せたらバカ受けした件
山歩きの楽しみの一つに「写真撮影」があります。苦労して見つけた石仏や遺跡、季節ご …
-
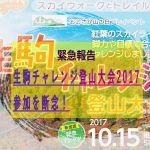
-
【緊急報告】今年の生駒チャレンジ登山大会への参加を断念!
第11回生駒チャレンジ登山2017への参加を断念することになりました。「なんでや …
-

-
下峠からの古道を歩く「学文峰と井谷ノ峰」
新ハイキング関西の山(1999年44号)の特選コースガイドで紹介された「静かな尾 …



